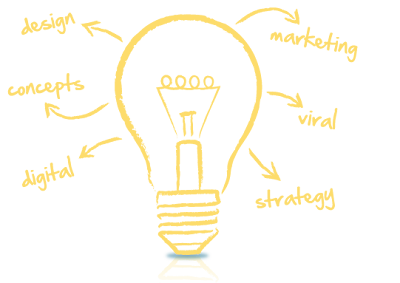大学時代に僕も実際に参加したStanford University内の組織が運営するプログラムの案内が今年も届いたのでブログにてご紹介。
サンフランシスコやシリコンバレーの起業家や社会起業家を訪問し、デザイン思考(design-thinking)を含む 具体的な哲学や手法を学び、実践していくことを目的としたプログラム、Exploring Social Innovation (ESI) Programは年明けから始まるプログラム。(事前研修-現地訪問-事後研修という流れ。)
僕はまだ学生だった一昨年のプログラムに参加したのですが、その中でTeach for AmericaやKiva、The Hubなどの他、d.schoolを訪問したり、IDEO出身の方にお話を伺ったりしました。(ちなみに現在の勤務先にもこのプログラム内の中で初めて訪問し、名刺をもらって喜んだりしていましたw)
僕自身は大学4年、社会人になる前の最後の春休みで行きましたが、非常に多くの出会いがあり、様々な刺激を受けたプログラムです。 学生のみなさま、忙しい春休みかと思いますが、予定があえば是非是非参加してみてくださいませ:)
以下詳細。
-----------------------------
Exploring Social Innovation (ESI) Programは、日本とアメリカの大学生を対象に、社会問題解決に向けた起業的手法をサンフランシスコ、シリコンバレーの社会起業家やNPOリーダーから学び、アメリカにおける社会イノベーションの最前線を体感し、デザイン思考やプレゼンテーション•スキルを身につける実践型のプログラムです。
【プログラム概要】
開催日時:2013年3月17日〜29日までの13日間
内容:2週間のプログラムでは、前半はサンフランシスコ、後半はスタンフォード大学において、以下のプログラムに参加します。
• シリコンバレーで活躍する社会起業家への訪問
• 社会的企業や非営利団体への訪問(過去訪問例:IDEO、Delancey Street、Room to Readなど)
• スタンフォード大学おいて、D-Schoolの教員による、デザイン思考(design-thinking)およびプレゼンテーションスキルのワークショップへの参加
• 米国で学んだ思考方法やフレームワークを活かして、グループ・ワークで日本の社会問題(教育、貧困等)の解決法を提案するプロジェクトの実施
【応募方法】
■参加費用: 3300ドル
(2週間の現地宿泊費、プログラム参加費、プログラム期間中の約3分の1の食事、現地交通費を含みます。)
■申し込み方法:申し込みフォーム(
http://www.viaprograms.org/esi/application)から、必要事項を英語で記入して、提出して下さい。
■申し込み締め切り:2013年1月5日
【お問い合わせ】 石田一統 (VIA, Senior Stanford Programs Director) kazutoh[a]viaprograms.org
-----------------------------
もしよろしければ、購読いただけると喜びます:)→

Twitterはこちら→